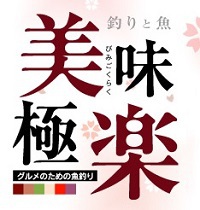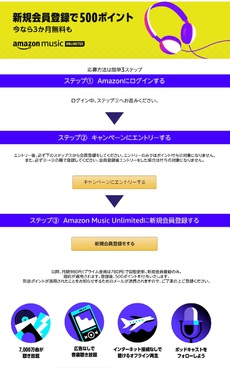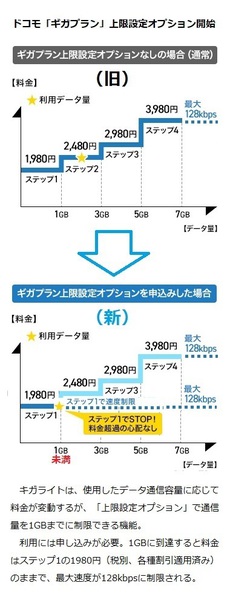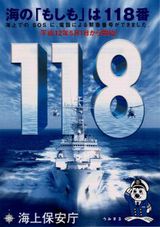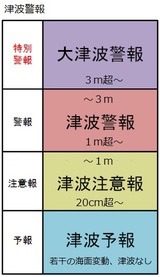2019年03月11日
カゴを作る、作り直す、天秤を作る、時の必需品、丸ペンチ!
カゴの自作、市販カゴの改良、天秤を自作する時など、
必ず必要になる工具が、丸ペンチ。
具体的には、芯棒を加工する=円形or楕円形を作る時に使用する。
具体的には、以下だね!

慣れるまでは、数回は失敗すると思うよ!
何でもそうだけど、ロスは考えて部材は余計に購入しておいた方が良い!
失敗してイライラするよりマシだと思ってる。
ってどんなもの?
ペンチの先端が、こんな感じのものです。

全体のシルエットは、こんな感じで先端部分?が円錐形になっている。

サイズ、いろいろあるけど、実際に使っているものを紹介しておきます。

ステン棒 1.8~2.0mm を曲げるなら以下のサイズ。
2.0mmを曲げるのに強度的に耐えている、これだろうね。。。
ただ握力が必要だけど、曲げるコツなどをマスターすれば、割と簡単に曲がる。
超高硬度ステン棒などは、加工する前に加熱して自然に冷やしてからだと少し曲げやすくなる。
整形を終えたら、また加熱し、今度は水につけ急激に冷やすと強度が戻る。
天秤など細かなもの加工する時に使っているのが、以下のサイズ。
1.8mm も曲がらないことはないと思うけど、2.0mm ではペンチが壊れそうで強度が足りない。。。。
丸ペンチは、カゴの自作や改造、天秤を自作するなら、上記の2本は必需品です!
ステン棒のカットや反りなどを調整するために、通常のペンチも必要。
ペンチの仕様でチェックするのは、 切断能力(鉄線)は要チェックです。
普通のペンチだと、1.6 ~ 1.8mm までなら何とか切れるが、、、
たった0.2 mm 差ではカットできず、カット専用を別途に購入した。
たかが、0.2mm だけど、されど 0.2mm !
普通のペンチで切ろうとするなら、毎回芯棒を90度回転させながら、ペンチで挟んで金づち叩く!
2回転もさせれば、そのうち切れる!
実際に使っているのは、デカすぎて?、カットするだけだからね。。。
気長が嫌な人は、以下のようなものを探すと良いと思うけど、使ってないから?
ただ、丸ペンチでステン棒を曲げても、
アールに反りが出てしまったり、楕円形にする時などの修正には使える。
どっちにしても握力は必要だと思うけどね。。。
参考 : ペンチ(200mm)
必ず必要になる工具が、丸ペンチ。
具体的には、芯棒を加工する=円形or楕円形を作る時に使用する。
具体的には、以下だね!

慣れるまでは、数回は失敗すると思うよ!
何でもそうだけど、ロスは考えて部材は余計に購入しておいた方が良い!
失敗してイライラするよりマシだと思ってる。
ってどんなもの?
ペンチの先端が、こんな感じのものです。

全体のシルエットは、こんな感じで先端部分?が円錐形になっている。

サイズ、いろいろあるけど、実際に使っているものを紹介しておきます。

ステン棒 1.8~2.0mm を曲げるなら以下のサイズ。
2.0mmを曲げるのに強度的に耐えている、これだろうね。。。
ただ握力が必要だけど、曲げるコツなどをマスターすれば、割と簡単に曲がる。
超高硬度ステン棒などは、加工する前に加熱して自然に冷やしてからだと少し曲げやすくなる。
整形を終えたら、また加熱し、今度は水につけ急激に冷やすと強度が戻る。
天秤など細かなもの加工する時に使っているのが、以下のサイズ。
1.8mm も曲がらないことはないと思うけど、2.0mm ではペンチが壊れそうで強度が足りない。。。。
丸ペンチは、カゴの自作や改造、天秤を自作するなら、上記の2本は必需品です!
ステン棒のカットや反りなどを調整するために、通常のペンチも必要。
ペンチの仕様でチェックするのは、 切断能力(鉄線)は要チェックです。
普通のペンチだと、1.6 ~ 1.8mm までなら何とか切れるが、、、
たった0.2 mm 差ではカットできず、カット専用を別途に購入した。
たかが、0.2mm だけど、されど 0.2mm !
普通のペンチで切ろうとするなら、毎回芯棒を90度回転させながら、ペンチで挟んで金づち叩く!
2回転もさせれば、そのうち切れる!
実際に使っているのは、デカすぎて?、カットするだけだからね。。。
気長が嫌な人は、以下のようなものを探すと良いと思うけど、使ってないから?
ただ、丸ペンチでステン棒を曲げても、
アールに反りが出てしまったり、楕円形にする時などの修正には使える。
どっちにしても握力は必要だと思うけどね。。。
参考 : ペンチ(200mm)
2019年03月03日
他のパーツについての質問について
タイトル「ほぼ完成70~80% 遠投かご」で、
この部分?の質問があったので、ここだと思うんですが。

上の赤枠のグリーンの玉コロ!
付けている理由は、かご全体が着水時に上方へ持ち上げられる。

上蓋部分の先端部分が、ステン棒のアール部分にぶつかり(押し付けられ)もろ衝撃が加わる。

緩衝材がないと、気持ち徐々に潰れて来る。
潰れて来ると上蓋の動きが、スムーズではなくなるような。。。
着水後、かごが開かずに棚まで一気に沈下するようにしても、、、

棚に届いたかごの上蓋が、スムーズに開閉しないと意味ないわけでね!
沈下速度や状態や浮力テストなら、ペットボトルで試せます。
ここで問題がなければ、実地テストでも問題はないと思います。
っで、コメントにあるパーツの件ですが。
いろいろと試した中で、これが耐久性も含めて最適かなと使っています。
※ 割れない・夜行玉ってのもある。
これ!
S : 直径=S/Φ5.5mm ・M : 直径=S/Φ7.5mm ・L : 直径=S/Φ9.5mm
センターの穴が細いので、芯棒に合わせでドリルの歯で穴を広げています。
芯棒は、2.0mmを使っているので、1.5~1.8mm の歯で拡大してから、2.0mm に広げています。
一気に広げると、広げすぎることがあったので、段階的に広げています。
これまでは、全て共通で「L 」サイズを使っていたんだけど、、、、
これ!
何か抵抗が大きいんじゃないかと、、、、
Mを装着してみたら、かごのサイズにして良い感じに仕上がった。
かごの下蓋分は、投げる時は正面で受ける空気抵抗が大きいと伸びが今一なような、、、、
かごの総体バランスは、
錘装着の下蓋部分とコマセを詰める上蓋分の総体バランスもあるけど、
後方へ流れる空気の流れもポイントが僅かでも上がるならと変えてみた。
自作かごもそうなんですが、ロングボディーは錘が重くないとバランスが悪くなる。
軽量かごは、かごのバランスが大事になる。
軽量錘でロングボディを使うと、飛行中に失速することが多い。。。
また、アミコマセが出きらないことがあったので、ロングボディはは使いません。
細身のボディは、オキアミをコマセに使うときは不利になる。
オキアミをコマセに使う時は、YAMASHITAの遠投シャトルを使ってますが、、、
ロケットかごMサイズなら、寸法を変えずに使えそうな気もしますが。
ロケットLサイズは、ロングボディーになるので止めた方が良い。
ついでだから、
芯棒は、焼きを入れて自然に冷やすと曲げやすくなる。
アールを作ったら、焼きを入れて急激に冷やすと強度がますみたい。
2.0mm のステン棒は、なかなかの硬さがあるので、毎回握力テストになる。
ロケットかごも凸凹が多いから、面取りをした方が良いような。
写真では見えませんが、凸部分はカッターで落としています。
遠投シャトルと自作かごのコマセ容量は、2 : 1位で自作かごの容量は半分くらい。
でも釣果に大差ないからね。。。。
自作かごよりは、きもちコマセ量が減りますが。。。
青物は当分先ですが、
これから真鯛の乗っ込みでしょかね。。。
この部分?の質問があったので、ここだと思うんですが。

上の赤枠のグリーンの玉コロ!
付けている理由は、かご全体が着水時に上方へ持ち上げられる。

上蓋部分の先端部分が、ステン棒のアール部分にぶつかり(押し付けられ)もろ衝撃が加わる。

緩衝材がないと、気持ち徐々に潰れて来る。
潰れて来ると上蓋の動きが、スムーズではなくなるような。。。
着水後、かごが開かずに棚まで一気に沈下するようにしても、、、

棚に届いたかごの上蓋が、スムーズに開閉しないと意味ないわけでね!
沈下速度や状態や浮力テストなら、ペットボトルで試せます。
ここで問題がなければ、実地テストでも問題はないと思います。
っで、コメントにあるパーツの件ですが。
いろいろと試した中で、これが耐久性も含めて最適かなと使っています。
※ 割れない・夜行玉ってのもある。
これ!
S : 直径=S/Φ5.5mm ・M : 直径=S/Φ7.5mm ・L : 直径=S/Φ9.5mm
センターの穴が細いので、芯棒に合わせでドリルの歯で穴を広げています。
芯棒は、2.0mmを使っているので、1.5~1.8mm の歯で拡大してから、2.0mm に広げています。
一気に広げると、広げすぎることがあったので、段階的に広げています。
これまでは、全て共通で「L 」サイズを使っていたんだけど、、、、
これ!
何か抵抗が大きいんじゃないかと、、、、
Mを装着してみたら、かごのサイズにして良い感じに仕上がった。
かごの下蓋分は、投げる時は正面で受ける空気抵抗が大きいと伸びが今一なような、、、、
かごの総体バランスは、
錘装着の下蓋部分とコマセを詰める上蓋分の総体バランスもあるけど、
後方へ流れる空気の流れもポイントが僅かでも上がるならと変えてみた。
自作かごもそうなんですが、ロングボディーは錘が重くないとバランスが悪くなる。
軽量かごは、かごのバランスが大事になる。
軽量錘でロングボディを使うと、飛行中に失速することが多い。。。
また、アミコマセが出きらないことがあったので、ロングボディはは使いません。
細身のボディは、オキアミをコマセに使うときは不利になる。
オキアミをコマセに使う時は、YAMASHITAの遠投シャトルを使ってますが、、、
ロケットかごMサイズなら、寸法を変えずに使えそうな気もしますが。
ロケットLサイズは、ロングボディーになるので止めた方が良い。
ついでだから、
芯棒は、焼きを入れて自然に冷やすと曲げやすくなる。
アールを作ったら、焼きを入れて急激に冷やすと強度がますみたい。
2.0mm のステン棒は、なかなかの硬さがあるので、毎回握力テストになる。
ロケットかごも凸凹が多いから、面取りをした方が良いような。
写真では見えませんが、凸部分はカッターで落としています。
遠投シャトルと自作かごのコマセ容量は、2 : 1位で自作かごの容量は半分くらい。
でも釣果に大差ないからね。。。。
自作かごよりは、きもちコマセ量が減りますが。。。
青物は当分先ですが、
これから真鯛の乗っ込みでしょかね。。。
2019年02月22日
ロケットかご改造の白い部分?
コメント欄に「 自作カゴの下蓋の白い部分は何を代用されたんでしょうか?」
多分、ロケットかごの改造 Ver,2 について以下の部分だと思うので載せておきます。

Ver,2 は、ロケットかごSサイズを使っています。
下蓋に使っているのが、以下のものを加工しています。

ロケットかご М/L なら、以下のものです。
自作かごのパーツとしては、以下のもの
上記は、かご1個製作に対して、2個必要ですが、、、
円錐型のものは、既に廃盤みたいです。
現在市販されtりるのは、6角形?のもの。
最初に、面取りをしてから加工する必要がある、面倒だけどね!!!
加工ロスが、完成品に対して10~20%は出ると思うので余計にストックした方が良いよ。
ただ、イレクターは、以前ほどバリエーションを見ないので製造が終わるかもね。。。
かごパーツは、自作かご完成品にして20個分前後はストックしてます。
自作かごのパーツは、市販かごの改造にも流用できるので無駄になることはないと思うよ!
錘は、自作かごも改造かごも共通で使っているのが、真鍮製の以下です。
錘は、かご釣りを始めた頃は鉛でしたが、
自作かごを作り始めて、1年も経たずに変更してます。
初期は、鉄?なのか、今でもストックしてますが、、、、
販売終了?の頃から今回の真鍮のシンカーを見つけて変更。。。
以来、自作かごのパーツに関するストックするようにしてます。
自作のかごの錘は、
・鉛だと加工中でも変形しやすい
・加工部の穴を一回り大きくしないといけない
・環境に悪い
ということで、、、
・加工中にも変形しない。
・変形しないので、加工部の穴を最小限に出来る。
・再利用?、スクラップ&ビルドが簡単!
・鉛より環境に優しい
真鍮?に変えています。
単価的では、鉛より高くなりますが、
っが!
芯棒との固着方法は、瞬間接着剤で十分なので、何回でも再利用が出来る!
結局、かごを作り直したりとすると、ランニングコストは鉛より割安になります。
ただ、重さの制約は出ますが、
最大35gってのはあります。
錘号数にすると、9.3号強って感じでしょか。
かご錘は、重くすれば飛ぶ?
竿を振り切れれば、SP+錘6号前後でも両軸並みに飛ぶよ!!!
最長飛距離?
コメントをもらっていたのを気づかず、、、に対する返答として書くかも。。。
多分、ロケットかごの改造 Ver,2 について以下の部分だと思うので載せておきます。

Ver,2 は、ロケットかごSサイズを使っています。
下蓋に使っているのが、以下のものを加工しています。

ロケットかご М/L なら、以下のものです。
自作かごのパーツとしては、以下のもの
上記は、かご1個製作に対して、2個必要ですが、、、
円錐型のものは、既に廃盤みたいです。
現在市販されtりるのは、6角形?のもの。
最初に、面取りをしてから加工する必要がある、面倒だけどね!!!
加工ロスが、完成品に対して10~20%は出ると思うので余計にストックした方が良いよ。
ただ、イレクターは、以前ほどバリエーションを見ないので製造が終わるかもね。。。
かごパーツは、自作かご完成品にして20個分前後はストックしてます。
自作かごのパーツは、市販かごの改造にも流用できるので無駄になることはないと思うよ!
錘は、自作かごも改造かごも共通で使っているのが、真鍮製の以下です。
錘は、かご釣りを始めた頃は鉛でしたが、
自作かごを作り始めて、1年も経たずに変更してます。
初期は、鉄?なのか、今でもストックしてますが、、、、
販売終了?の頃から今回の真鍮のシンカーを見つけて変更。。。
以来、自作かごのパーツに関するストックするようにしてます。
自作のかごの錘は、
・鉛だと加工中でも変形しやすい
・加工部の穴を一回り大きくしないといけない
・環境に悪い
ということで、、、
・加工中にも変形しない。
・変形しないので、加工部の穴を最小限に出来る。
・再利用?、スクラップ&ビルドが簡単!
・鉛より環境に優しい
真鍮?に変えています。
単価的では、鉛より高くなりますが、
っが!
芯棒との固着方法は、瞬間接着剤で十分なので、何回でも再利用が出来る!
結局、かごを作り直したりとすると、ランニングコストは鉛より割安になります。
ただ、重さの制約は出ますが、
最大35gってのはあります。
錘号数にすると、9.3号強って感じでしょか。
かご錘は、重くすれば飛ぶ?
竿を振り切れれば、SP+錘6号前後でも両軸並みに飛ぶよ!!!
最長飛距離?
コメントをもらっていたのを気づかず、、、に対する返答として書くかも。。。
2019年02月01日
ほぼ完成70~80% 遠投かご
ロケットカゴ Ver,2 といったところでしょうか。
パーツを眺めながら、ようやく組立て70~80% まで完成?
まだ改良余地を残しているので、パーツの固着はしていないけどね。
上蓋部分の浮力材を付けていない。
浮力の付け方を変える予定なので。
でも、まぁ~安価に遠投カゴを作りたい人には、、、、
こんな感じですので、参考まで!!!
カゴ総重量は、25gです。
このカゴだとウキは6g前後なので、ウキ+カゴ≒31g。
この重さなら、竿の錘負荷40g(約10号)もあれば最適?
モバイルロッドや重り負荷の少ないロッド用に作ったので。。。

試し投げは、これからだけど、
遠投性は、自作カゴよりは劣ると思うけど未改良の市販カゴよりは遥かに飛ぶはず!
ちなみに錘は4号位だと思うけど、5m前後の竿なら80m前後は飛ぶはず。
飛距離は、竿の長さにも関係するので、短くなれば飛距離は縮むか。。。

蓋の空き具合もまぁまぁだと思う。
巻き上げる時も、蓋が閉まらないとダメだしね~!
とは言っても、改良余地は、まだ浮力の他にも残しているので。。。
あとは自分で考えて下さいね!!!
ヒントは、空力特性もあるね!
パーツを眺めながら、ようやく組立て70~80% まで完成?
まだ改良余地を残しているので、パーツの固着はしていないけどね。
上蓋部分の浮力材を付けていない。
浮力の付け方を変える予定なので。
でも、まぁ~安価に遠投カゴを作りたい人には、、、、
こんな感じですので、参考まで!!!
カゴ総重量は、25gです。
このカゴだとウキは6g前後なので、ウキ+カゴ≒31g。
この重さなら、竿の錘負荷40g(約10号)もあれば最適?
モバイルロッドや重り負荷の少ないロッド用に作ったので。。。
試し投げは、これからだけど、
遠投性は、自作カゴよりは劣ると思うけど未改良の市販カゴよりは遥かに飛ぶはず!
ちなみに錘は4号位だと思うけど、5m前後の竿なら80m前後は飛ぶはず。
飛距離は、竿の長さにも関係するので、短くなれば飛距離は縮むか。。。
蓋の空き具合もまぁまぁだと思う。
巻き上げる時も、蓋が閉まらないとダメだしね~!
とは言っても、改良余地は、まだ浮力の他にも残しているので。。。
あとは自分で考えて下さいね!!!
ヒントは、空力特性もあるね!
2019年01月22日
かごの浮力の付け方
かごの浮力の付け方
かごの水中でコマセが放出されなければ、役立たず!
素材で浮力の有無もあるけれど、、、
着実に棚でコマセ散布をさせる為に、かごの上蓋に浮力を加えています。
まずは、余った?失敗した?軟質発泡を用意する。

上蓋の内側に接着剤を塗りてから、軟質発泡を押し込む!
゛むっぎゅ”と、奥まで押し込む!

押し込むと、こんな感じかね!

押し込み終えて接着剤が乾燥しただろう2~3時間以上も放置したら、
焼きごて?、ドライバーでも何でも良いけど、
壁面に沿って軟質発泡を溶かす!
数ミリは残しておくことで浮力が稼げる、これポイント!

ただし、センター部分は、少し厚みを残しておく!
まぁ~これで、コマセを入れた状態でも水中で浮き上がる!はず!
かごの水中でコマセが放出されなければ、役立たず!
素材で浮力の有無もあるけれど、、、
着実に棚でコマセ散布をさせる為に、かごの上蓋に浮力を加えています。
まずは、余った?失敗した?軟質発泡を用意する。
上蓋の内側に接着剤を塗りてから、軟質発泡を押し込む!
゛むっぎゅ”と、奥まで押し込む!
押し込むと、こんな感じかね!
押し込み終えて接着剤が乾燥しただろう2~3時間以上も放置したら、
焼きごて?、ドライバーでも何でも良いけど、
壁面に沿って軟質発泡を溶かす!
数ミリは残しておくことで浮力が稼げる、これポイント!
ただし、センター部分は、少し厚みを残しておく!
まぁ~これで、コマセを入れた状態でも水中で浮き上がる!はず!